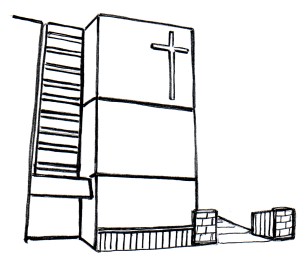 東京の教会(その24)
東京の教会(その24)洗足教会1991.12.22
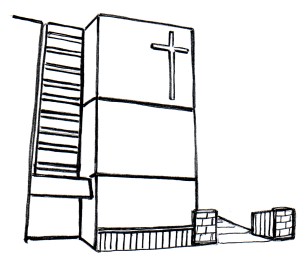 東京の教会(その24)
東京の教会(その24) 東京の教会訪問は23区内のミサが行われる教会はこの洗足教会が最後になりました。ここ2,3回目のなかで選んで洗足教会を最後に残したのは訳があります。皆さんもすぐ分かったでしょう「洗足」といえばカトリック信者にとって特別の思い入れがありますね。聖木曜日の夜イエス様は使徒達の足を洗われました。洗足式ということもあります。江戸の地名にまさかキリストの洗足式のいわれがあるとはとても思えませんが、楽しみでした。 教会は山手線「五反田」から東急池上線に乗り換えて5つ目「長原」で降りて歩いて5分でした。教会の建物は由緒ある教会というイメージの、内陣、身廊に側廊までありました。内陣の祭壇は木製のゴシック教会を形取った豪華なものでした。
椅子は木製で磨きこまれており、ひざまづく台は取外してありました。椅子を沢山前につめるためのようでした。教会の建物といい、この椅子の様子といい、確か板橋の教会と大変よくにていました。一番前の席には、「第2朗読者席」というプラスチック板の表示がありました。第1朗読者席はちょっと見当たりませんでした。
司式は青山神父様で来年の3月で71才、昨日の12月21日で叙階40年になるということでしたが、大変元気な様子でした。お話はさすがにしみじみとした落着いたもので感銘をうけました。信者席は160程でしたが、聖体拝領は120人程でした。お知らせは神父様がされましたが、明日の23日午後3時からここの聖堂でチャリティーコンサートが開かれるということ、元旦のミサは7時と11時ということでした。
ミサ後、この付近に洗足池があるので訪れてみました。先程降りた「長原」の次に洗足駅がありすぐその前に池があり、洗足公園になっています。そこの案内の掲示でわかりました。昔ここらあたりは千束と呼ばれていました。日蓮上人がここにとおりかかり、袈裟をぬいで側の松の木に掛け、池で足を洗われました。そこから洗足池と呼ばれるようになり、この付近が洗足と呼ばれるようになったのです。袈裟掛の松の3代目が残っていました。また明治維新に活躍した勝海舟の墓も近くにありましたが、午後会社に出なければならないのでそこまで行く時間がなく残念ながら帰宅を急ぎました。
おわりに
しばらく続いた東京の教会の便りも、私が一回りしたここでいったん終りにさせていただきます。昨年の4月から数えて23教会を紹介したことになります。皆さんから同情される単身赴任ですが、見方を変えれば、この機会だからこそ50近い教会を全部回ることができたので本当に嬉しいことです。しかし次から次へ新しいところへ行くのも気疲れするもので、これからはもう一度行ってみたいところ、巡回教会、都下の周辺の市の教会など少し気楽に尋ねて見ようと思います。そのときまた皆さんに紹介する内容があれば記事をお送りします。
毎回新しい聖堂で初めての神父様の話を聞き新しい雰囲気でミサに預かることは多分皆さんから羨ましがられるほどのことではあると思いますが、これは一つの見方であって、毎週同じ聖堂で同じ神父様の話で同じ雰囲気でも「自分の気持ちが1週間の間に新しくなっていれば必ず新しい素晴らしさが発見できるもので、それがミサの秘跡ではないか」と考えるようになりました。これは朗読を頼まれたり、ミサ後紹介されたりすることで気付いたことです。
また、何度か書きましたが、初めて訪れたとき掲示板、案内版の一言が大変嬉しく、特に聖書と典礼や聖歌集を手渡されたり、声を掛けられたりするとどんなに気持ちが安らぐか、自分で体験して初めてわかります。これはぜひ衣笠でも「見かけない人」に対して出来ることから行われることをおすすめします。