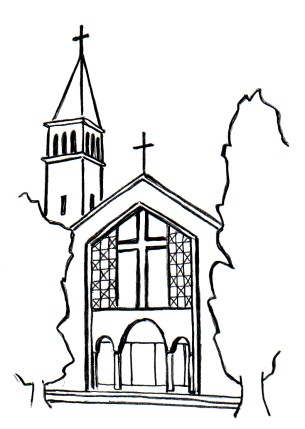 東京の教会(その19)
東京の教会(その19)下井草教会1991.11. 3
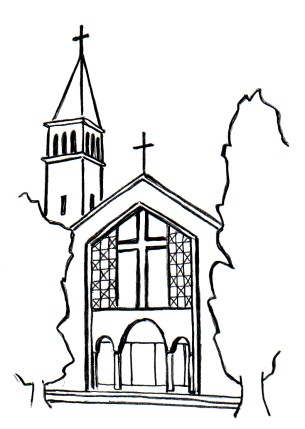 東京の教会(その19)
東京の教会(その19) JR高田の馬場から西武新宿線に乗換えて各停で8つめに下井草という駅があり、そこから10分程で下井草教会があります。ゴシック風の尖塔の十字架が遠くからでも見えますのですぐわかります。東京の聖堂のなかでもかなり広い方で、長方形の堂内にはゆっくりと300人は入れる椅子が整然と並んでいました。正面にはステンドグラスのもとに祭壇が教会模型のように鮮やかな色彩で飾られています。
ミサの前に「お告げの祈り」とロザリオを1連唱えました。司祭が3人入場されましたが、主任司祭とお兄さんの司祭ともう一人の神父さまでした。お兄さんの司祭はここ1か月この教会にお客としていましたが明日からローマに戻って教皇様のところで働くということでした。教会の壮大さに相応しく、司祭3人に侍者が白い祭服の青年が3人、赤い祭服の小さな子供が5人いました。
歌ミサでしたが歌は私にとって初めてのものでした。しかし日本的な様式ながらパイプオルガンにあったとても荘重なものでした。
説教はローマに帰るお兄さんの神父様でしたがとても素晴らしいものでした。この説教も内容といい訴える迫力といい東京の数多くのミサの中で聞いたものでも有数のもので、さすがだと思いました。話は「キリストの愛は自分と神様の間の縦のものと、隣人同志の横のものが組合わさった十字架の姿が真実の愛であり、どちらが欠けても本当の愛ではない」ということが中心でした。
共同祈願の答唱は「主よ私達の祈りを聞き入れて下さい」でした。献金は女の子8人が揃いの水色の肩掛けをして整然と行列して、2人ずつ組になり、赤いビロードのぬので飾られた籠を順次信者席に回していき、集め終わったら祭壇の右に置いてあるテーブルの上にのせました。
聖変化のときには白い青年侍者を中心に赤い子供侍者が両側に2人ずつ白い手袋をはめて槍のような長いろうそく台を手にして祭壇に向かって信者席の一番前に並び、その後ろに献金を集めた青い少女8人が横に並びました。その動きと形は本当に整然たるもので、いささか時代がかった様子ではありましたがある種の感動を覚えました。
ミサの終わりに、終わりの祈りと、十字架上のイエズスに捧げる祈りと、司祭の召出しを願う祈りをしました。
今日この下井草教会にしたのは、実は例の「エポペ」で出会った土屋神父様がこちらの教会であり、11月3日にバザーがあるから是非いらっしゃいと誘われたので、東京に来ている家内と一緒に来たものです。ところが教会にはいってもバザーの様子はない、お知らせでは先週すんだようでした。また3人のミサの司祭にも土屋神父の姿は見えない、先の兄弟の神父は尻枝神父という方でした。どうも私の聞き違いかなと首をかしげながらミサの終わりかけるころようやく合点がいきました。教会の隣に育英工業高等専門学校があり、教会に入る前にそこでバザーをやっていることに気付きました。そこがカトリック系の学校ではないかと教会所在地の本を見ると確かに教育関係施設として載っていました。安心して聖堂を出たところでやはり土屋神父がおられました。挨拶をすませ、帰りにその学校のバザーに立寄りました。