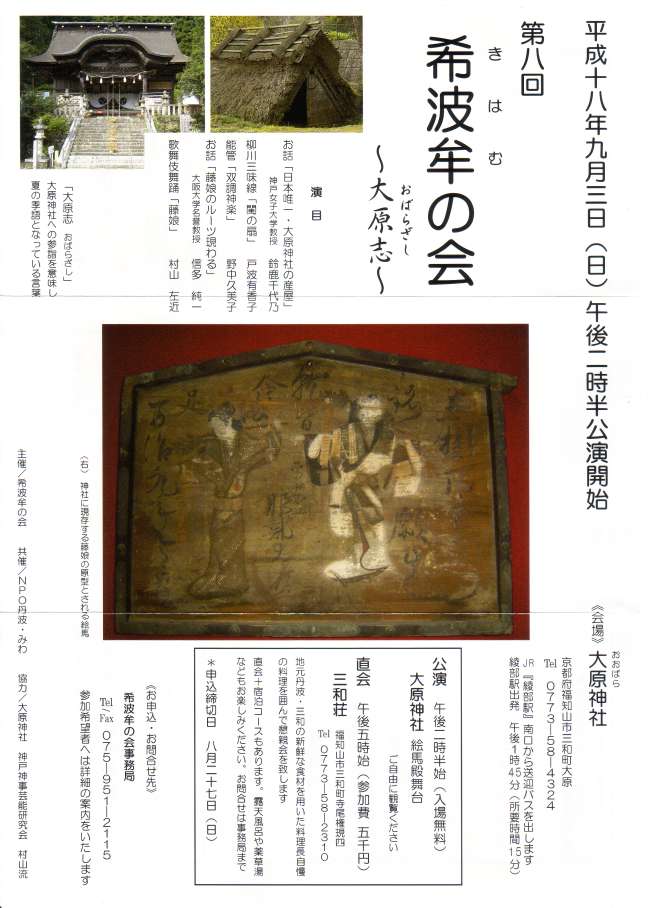
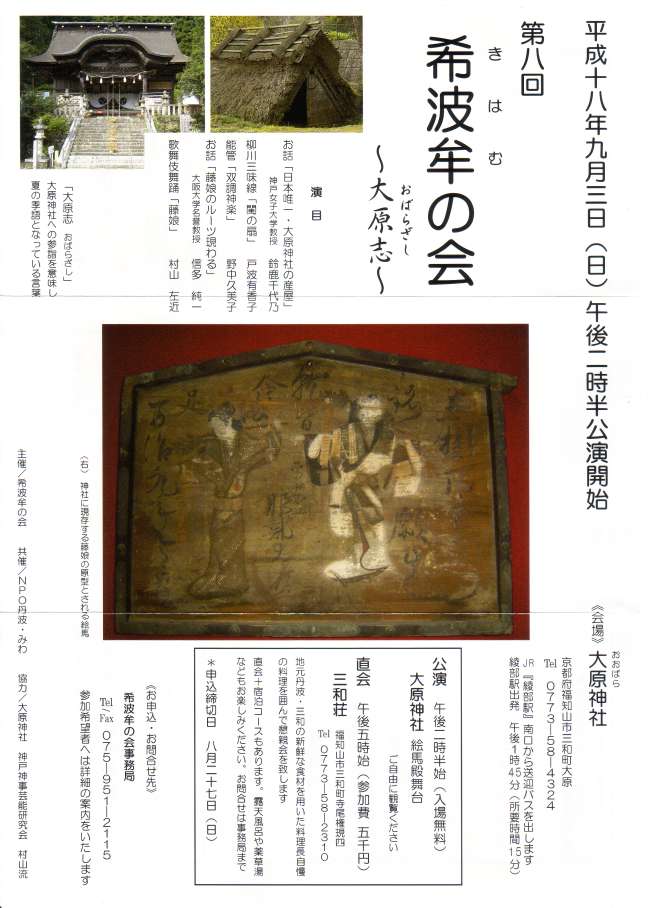
2006年9月3日(日) 福知山市大原神社で希波牟の会の公演が行われました。
公演に先立って、戸波有香子先生(箏)と野中久美子先生(能管)が、NPO法人「丹波・みわ」のインタビューを受けて語りました。その要点をご紹介しましょう。
希波牟の会というのは
野中 希波牟というのは芸を極めるということで、「きわむ」に万葉仮名を当てているのです。つまり、それぞれ違う分野で活動する者がそれぞれの芸を究めるという意味です。究めるなんて、ちょっとおこがましいかも知れませんが、そういう志を持ってやっていると。
戸波 今回の大原神社に限らず、希波牟の会では、訪れた地域にちなむ演目ですとか、あるいは神社・お寺の演技にちなむことですとか、そういうことで、なるべくその場所その季節に催す意味のある内容ということ、そして芸能の始まりはもともと神や仏にさざける事から始まったということを大切にしたいと考えています。
今回大原神社で公演されることになったのは?
野中 鈴鹿先生(希波牟の会同人)が古事記の研究をしておられるのですが、古事記にも産屋というのが出てきまして、そういうことでとても関心深かったのです。それに、私は、何年か前、大原神社の1050年祭のときに呼んでいただきました、その後も何度かお参りに寄せていただいています。静かでとてもすてきな場所ですね。
戸波 今回の大原神社に限らず、希波牟の会では、訪れた地域にちなむ演目ですとか、あるいは神社・お寺の縁起にちなむことですとか、そういうことで、なるべくその場所その季節に催す意味のある内容ということ、そして芸能の始まりはもともと神や仏にささげることから始まったということを大切にしたいと考えています。
お2人とも、もともとは、クラシックなど洋楽をやっておられたわけですね。
野中 私は、小さい頃はピアノでしたし、大学のときは、バイオリンを練習していました。笛を始めたのは29歳からでとても遅いのです。以前から関心はありましたが何か特別にきっかけがあったわけではないのです。
どうして能管かということですが、私の楽器のような気がしたということで、人と人とのご縁も天の定めですけど、楽器と人の出会いも天の定めみたいなものかなと。
戸波 私はこどものころからマリンバ、エレクトーン、ピアノ、テナーサックスなどの楽器がおもちゃだったんです。私が箏を習い始めたきっかけは、ある日倉を整理していたら大きな桐の箱が出て来たんです。その中に楽器が入っているとは知らずに組み紐を解いて箱を開けたらお箏が出てきて、ちょっとお稽古でもしてみようなかということになって。
それで習い始めたのですが、今までたくさん関わった楽器の中で、なぜお箏やお三味線と強く関わって行くことになったかというと、やっぱり分からないですね。
大げさに言えばきっとお箏や三味線が私を選んでくれたんじゃないかなと。ただ、日本人としてとてもしっくり来ることは、確かです。
NPO法人丹波・みわのお許しをいただいて、機関紙「丹波みわ」2006年9月号vol.33から一部転載させていただきました。