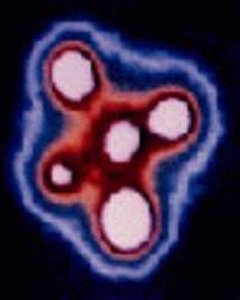 アインシュタインの十字架
アインシュタインの十字架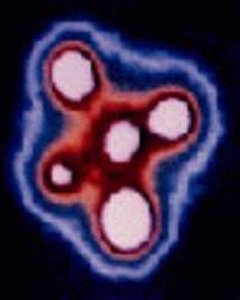 アインシュタインの十字架
アインシュタインの十字架「アインシュタインの望遠鏡」という本を読んでいたら、アインシュタインの十字架というのが出てきました。アインシュタインの望遠鏡というのは、相対性理論により、重力により光りが曲がるという原理を利用しています。太陽の影に隠れた星からの光りがまっすぐ進むと地球には届かないのに、太陽の横を通るときに内側に曲げられるため見えます。ガラスの凸レンズを考えると、焦点より離れた点から出た光がレンズを通ると、反対側の焦点より遠いところに光が集まります。これと同じように、重力が大きい銀河の裏にある星がその銀河に隠れるのではなくて地球で観測することが出来るのです。
そのレンズはガラスのようにきちんとした形ではないので、地球に来る光はゆがんで、蜃気楼のようなゴーストが出来ます。これが4つ出来たのがアインシュタインの十字架と呼ばれます。上右の写真はその一例です。裏の星はクエーサーと呼ばれる星の1つで、真ん中はレンズの役割を果たした銀河です。
 |
 |
| アンドロメダ大星雲 | 馬頭星雲 |
この十字架の写真を見たとき、高校時代に初めてアンドロメダ大星雲とか、馬頭星雲の写真を見たときの興奮を思い出しました(当時の写真はモノクロでした)。人工衛星に搭載したNASAのハッブル宇宙望遠鏡で観測したもので、当時は考えもしなかった技術の進歩で見ることが出来たわけです。もっともそのころは「不思議の国のトムキンス」を読んでいて、相対性理論の奇妙さに惹かれた頃でもありますが。