かぎりない愛
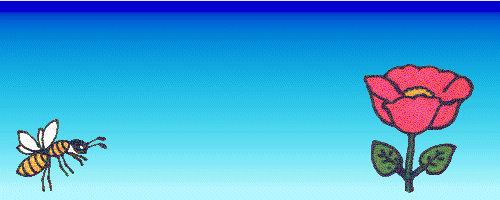
はちはお花のなかに、お花はお庭のなかに、お庭は土べいのなかに、土べいは町のなかに、町は日本のなかに、日本は世界のなかに、世界は神さまのなかに。
そうして、そうして、神さまは、小ちゃなはちのなかに。
これは前世紀(1900年)の初め、山口県で生まれ、26才で亡くなった童謡詩人、金子みすずの「はちと神さま」という詩です。
この詩を私が初めて知ったのは、今から10年近く年前東京に単身赴任していたとき、銀座の朝日ホールにおいてシティズンズ・カレッジの講演で科学者の佐治晴夫氏の話を聞いたときです。
ドイツの数学者リヒヤルト・デテキント(1831〜1916)は「全体のなかに個があり、個のなかに全体がある」ことを「無限」と定義しました。
金子みすずはキリスト信者ではなかったと思いますが、神は「無限」であることを直感しているように思えます。
カトリックの神言会の西 経一神父は、カトリック京都司教区の聖書講座で次のように話されました。「神は私を一番愛している。神は世界の誰を愛するよりも、自分を一番愛している」
人間社会では、特に男女の関係では、いろいろな女性に「僕は君を世界一愛しているよ」と言えば、それは嘘をついていることになります。
そうして、そうして、神さまは、小ちゃなはちのなかに。
これは前世紀(1900年)の初め、山口県で生まれ、26才で亡くなった童謡詩人、金子みすずの「はちと神さま」という詩です。
この詩を私が初めて知ったのは、今から10年近く年前東京に単身赴任していたとき、銀座の朝日ホールにおいてシティズンズ・カレッジの講演で科学者の佐治晴夫氏の話を聞いたときです。
ドイツの数学者リヒヤルト・デテキント(1831〜1916)は「全体のなかに個があり、個のなかに全体がある」ことを「無限」と定義しました。
金子みすずはキリスト信者ではなかったと思いますが、神は「無限」であることを直感しているように思えます。
カトリックの神言会の西 経一神父は、カトリック京都司教区の聖書講座で次のように話されました。「神は私を一番愛している。神は世界の誰を愛するよりも、自分を一番愛している」
人間社会では、特に男女の関係では、いろいろな女性に「僕は君を世界一愛しているよ」と言えば、それは嘘をついていることになります。
無限の神、「限りない愛」の神にとっては、ある人を世界の誰よりも愛し、別な人を世界の誰よりも愛すということは、全く矛盾しないことになるのではないでしょうか。それは誰に対しても「同じように愛する」、「平等に愛する」のではなく、「誰よりも一番愛する」のです。だから私も、「神は世界の誰を愛するよりも私を一番愛している」と信じています。
無限大というのは、数学の記号では数字の8の字を横にした「∞」で表します。この無限大の世界はとても面白いのですが、たとえば、この無限大を二人で分けても一人分は無限大、何人で分けても一人分は無限大、まるで神さまのようです。
この無限の神、「かぎりない愛」の神であることを考えると、ジョン・ヒックの「宗教多元論」が頭をかすめています。